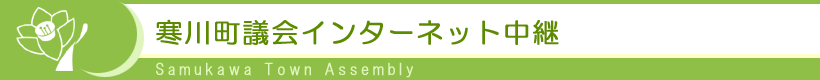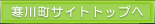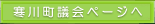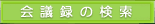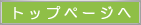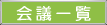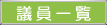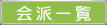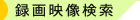eyJwbGF5ZXJLZXkiOiJjYmJlMDljOS0yYzc0LTQwNDEtOWJkNC1iYjZlY2UzYjk0MDAiLCJhbmFseXRpY3NLZXkiOiI5ZWM4YTVlMS1lNWNkLTRkMzUtYTFlMC0wOTE4MWYzOTQwMDYiLCJpc0xpdmUiOmZhbHNlLCJ0aXRsZSI6InNhbXVrYXdhLXRvd25fMjAyMzAzMDlfMDAzMF95YWdpc2hpdGEtbWFzYWtvIiwicGxheWVyU2V0dGluZyI6eyJwb3N0ZXIiOiIvL3NhbXVrYXdhLXRvd24uc3RyZWFtLmpmaXQuY28uanAvaW1hZ2UvdGh1bWJuYWlsLmpwZyIsInNvdXJjZSI6Ii8vc2FtdWthd2EtdG93bi5zdHJlYW0uamZpdC5jby5qcC8/dHBsPWNvbnRlbnRzb3VyY2UmdGl0bGU9c2FtdWthd2EtdG93bl8yMDIzMDMwOV8wMDMwX3lhZ2lzaGl0YS1tYXNha28maXNsaXZlPWZhbHNlIiwiY2FwdGlvbiI6eyJlbmFibGVkIjoiZmFsc2UiLCJwYXRoIjoiIn0sInRodW1ibmFpbCI6eyJlbmFibGVkIjoiZmFsc2UiLCJwYXRoIjoiIn0sIm1hcmtlciI6eyJlbmFibGVkIjoiZmFsc2UiLCJwYXRoIjoiIn0sInNwZWVkY29udHJvbCI6eyJlbmFibGVkIjoiZmFsc2UiLCJpdGVtIjpbIjAuNSIsIjEiLCIxLjUiLCIyIl19LCJza2lwIjp7ImVuYWJsZWQiOiJmYWxzZSIsIml0ZW0iOlsxNV19LCJzdGFydG9mZnNldCI6eyJlbmFibGVkIjoiZmFsc2UiLCJ0aW1lY29kZSI6MH0sInNlZWtiYXIiOiJ0cnVlIiwic2RzY3JlZW4iOiJmYWxzZSIsInZvbHVtZW1lbW9yeSI6ZmFsc2UsInBsYXliYWNrZmFpbHNldHRpbmciOnsiU3RhbGxSZXNldFRpbWUiOjMwMDAwLCJFcnJvclJlc2V0VGltZSI6MzAwMDAsIlBsYXllclJlbG9hZFRpbWUiOjMwMDAsIlN0YWxsTWF4Q291bnQiOjMsIkVycm9yTWF4Q291bnQiOjN9fSwiYW5hbHl0aWNzU2V0dGluZyI6eyJjdXN0b21Vc2VySWQiOiJzYW11a2F3YS10b3duIiwidmlkZW9JZCI6InNhbXVrYXdhLXRvd25fdm9kXzEwNDYiLCJjdXN0b21EYXRhIjp7ImVudHJ5IjoicHVibGljIn19fQ==
- 令和5年第1回定例会 3月会議
- 3月9日 本会議(一般質問)
- フォーラム寒川 柳下 雅子 議員
1.「子どもの政策」の推進策について
1924年に児童の権利に関するジュネーブ宣言が出されてから、まもなく100年になる。
1946年 日本国憲法が制定
1948年 教育勅語廃止
1951年 児童憲章制定
1989年 児童の権利に関する条約が国連総会で採択
1990年 日本が109番目の署名国となる
という歴史的経過を経て、国は2023年4月より、「こども基本法」を施行。6つの基本理念に基づき地方公共団体は子ども施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつその区域内における子どもの状況に応じて施策を策定し実施する責務を有するとされている。こども基本法の意義と活用をどのように捉えているのか。地域的な視点からまちづくりの当事者として主体的に関わる環境づくりが大事だと考える。
子ども施策推進に向けての具体策についての見解を問う。
1924年に児童の権利に関するジュネーブ宣言が出されてから、まもなく100年になる。
1946年 日本国憲法が制定
1948年 教育勅語廃止
1951年 児童憲章制定
1989年 児童の権利に関する条約が国連総会で採択
1990年 日本が109番目の署名国となる
という歴史的経過を経て、国は2023年4月より、「こども基本法」を施行。6つの基本理念に基づき地方公共団体は子ども施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつその区域内における子どもの状況に応じて施策を策定し実施する責務を有するとされている。こども基本法の意義と活用をどのように捉えているのか。地域的な視点からまちづくりの当事者として主体的に関わる環境づくりが大事だと考える。
子ども施策推進に向けての具体策についての見解を問う。