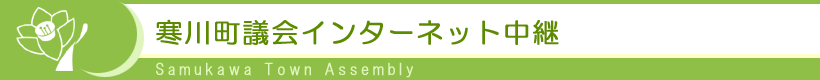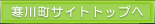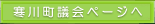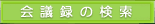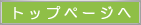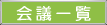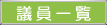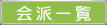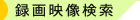eyJwbGF5ZXJLZXkiOiJjYmJlMDljOS0yYzc0LTQwNDEtOWJkNC1iYjZlY2UzYjk0MDAiLCJhbmFseXRpY3NLZXkiOiI5ZWM4YTVlMS1lNWNkLTRkMzUtYTFlMC0wOTE4MWYzOTQwMDYiLCJpc0xpdmUiOmZhbHNlLCJ0aXRsZSI6InNhbXVrYXdhLXRvd25fMjAyNDEyMTBfMDAzMF9rb2l6dW1pLXNodXVzdWtlIiwicGxheWVyU2V0dGluZyI6eyJwb3N0ZXIiOiIvL3NhbXVrYXdhLXRvd24uc3RyZWFtLmpmaXQuY28uanAvaW1hZ2UvdGh1bWJuYWlsLmpwZyIsInNvdXJjZSI6Ii8vc2FtdWthd2EtdG93bi5zdHJlYW0uamZpdC5jby5qcC8/dHBsPWNvbnRlbnRzb3VyY2UmdGl0bGU9c2FtdWthd2EtdG93bl8yMDI0MTIxMF8wMDMwX2tvaXp1bWktc2h1dXN1a2UmaXNsaXZlPWZhbHNlIiwiY2FwdGlvbiI6eyJlbmFibGVkIjoiZmFsc2UiLCJwYXRoIjoiIn0sInRodW1ibmFpbCI6eyJlbmFibGVkIjoiZmFsc2UiLCJwYXRoIjoiIn0sIm1hcmtlciI6eyJlbmFibGVkIjoiZmFsc2UiLCJwYXRoIjoiIn0sInNwZWVkY29udHJvbCI6eyJlbmFibGVkIjoiZmFsc2UiLCJpdGVtIjpbIjAuNSIsIjEiLCIxLjUiLCIyIl19LCJza2lwIjp7ImVuYWJsZWQiOiJmYWxzZSIsIml0ZW0iOlsxNV19LCJzdGFydG9mZnNldCI6eyJlbmFibGVkIjoiZmFsc2UiLCJ0aW1lY29kZSI6MH0sInNlZWtiYXIiOiJ0cnVlIiwic2RzY3JlZW4iOiJmYWxzZSIsInZvbHVtZW1lbW9yeSI6ZmFsc2UsInBsYXliYWNrZmFpbHNldHRpbmciOnsiU3RhbGxSZXNldFRpbWUiOjMwMDAwLCJFcnJvclJlc2V0VGltZSI6MzAwMDAsIlBsYXllclJlbG9hZFRpbWUiOjMwMDAsIlN0YWxsTWF4Q291bnQiOjMsIkVycm9yTWF4Q291bnQiOjN9fSwiYW5hbHl0aWNzU2V0dGluZyI6eyJjdXN0b21Vc2VySWQiOiJzYW11a2F3YS10b3duIiwidmlkZW9JZCI6InNhbXVrYXdhLXRvd25fdm9kXzEyNzgiLCJjdXN0b21EYXRhIjp7ImVudHJ5IjoicHVibGljIn19fQ==
- 令和6年第1回定例会 12月会議
- 12月10日 本会議(一般質問)
- 会派に属さない議員(令和5年3月~令和6年12月) 小泉 秀輔 議員
1.人口減少への対応について
これまで、町においては家屋の建設増加などに伴い転入者も多く、少子高齢化による自然減を社会増が上回る状況が続き、少しずつであるが人口は増加を続けてきた。だが昨年度以降、統計上はいよいよ人口が減少期に入る兆しを見せている。人口推計からも将来的な人口減少はほぼ確実であり、その中でも財政を維持し行政サービスを守っていくことや、町の活力を維持していくことは大きな課題となっている。
人口減少を少しでも食い止めるためにはおおよそ3つの方法、出生数の増加、転入者の増加、転出者の減少を目指すことがあるかと思われる。
いずれの方法にしても、やはり住民が暮らしやすい、住んで良かったと思える総合的なまちづくりが求められる。
そこで町としてはどのような対策によって人口減少を食い止めることを目指すのか、住宅政策や保育・子育て環境、産業経済政策や安全・安心対策などの観点から、そのビジョンや施策について問う。
これまで、町においては家屋の建設増加などに伴い転入者も多く、少子高齢化による自然減を社会増が上回る状況が続き、少しずつであるが人口は増加を続けてきた。だが昨年度以降、統計上はいよいよ人口が減少期に入る兆しを見せている。人口推計からも将来的な人口減少はほぼ確実であり、その中でも財政を維持し行政サービスを守っていくことや、町の活力を維持していくことは大きな課題となっている。
人口減少を少しでも食い止めるためにはおおよそ3つの方法、出生数の増加、転入者の増加、転出者の減少を目指すことがあるかと思われる。
いずれの方法にしても、やはり住民が暮らしやすい、住んで良かったと思える総合的なまちづくりが求められる。
そこで町としてはどのような対策によって人口減少を食い止めることを目指すのか、住宅政策や保育・子育て環境、産業経済政策や安全・安心対策などの観点から、そのビジョンや施策について問う。